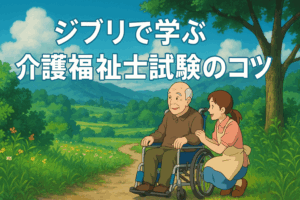✅【介護福祉士試験】認知症の理解⑪
〜認知症と薬の話。飲んだら治るん?〜🧠ここだけは抑えとけ|「薬で治る」とは限らんねん編
✏️「薬と認知症」系導入文
「薬を飲めば治るんやろ?」ってよく聞かれるけど、
**認知症の薬は“治す”んやなくて、“進行をゆるやかにする”**もんやねん。
人によって合う薬も副作用も違うから、正しい理解と観察が大事やで!
📘認知症治療薬の基本
| 薬の種類 | 代表例 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| コリンエステラーゼ阻害薬 | ドネペジル(アリセプト) リバスチグミン(イクセロン) ガランタミン(レミニール) | 記憶・学習機能の改善 主にアルツハイマー型に使われる |
| NMDA受容体拮抗薬 | メマンチン(メマリー) | 興奮性神経の過剰刺激を抑える 中等度〜重度のアルツハイマー型に使われる |
👉薬は「対症療法」やで
- 認知症の進行を完全に止めたり治したりする薬は今のところない
- 一時的に症状が改善したり、落ち着くことはある
- BPSD(周辺症状)に対して抗精神病薬や抗うつ薬が使われることもあるが、副作用にも注意が必要
🎞ジブリ風に言うなら?
『もののけ姫』でサンが「命を取り戻す薬草」を持ってたやろ?
でも、それで“呪い”自体が消えたわけやない。進行を遅らせただけ。
認知症の薬もそれと一緒。
進行を和らげたり、今を少し楽にする“手助け”ってことやで。
💡現場で活かせる小ワザ
- 薬の飲み忘れ・重複投与に注意
- 飲んだ後の変化(興奮、眠気、食欲低下など)をしっかり観察
- 本人が嫌がる場合は「お茶で一緒に飲む」など工夫を
- 医師や薬剤師との連携が超大事!気になる副作用はすぐ報告
🧠試験で出るポイント!
| 用語 | 内容・補足 |
|---|---|
| ドネペジル(アリセプト) | アルツハイマー型認知症に使用/進行抑制 |
| メマンチン(メマリー) | 興奮性神経の過剰反応を抑える/中等度以上 |
| 対症療法 | 病気の原因ではなく、症状を和らげる治療法 |
| 副作用 | 食欲不振、興奮、便秘、めまいなどがある場合も |
🎯今日のキーワードは?
📌**「薬=治る」ではない。
でも、正しく使えば“今”を楽にする力がある。**
介護職は“薬の変化”に一番近くで気づける存在やで!
📖おさらいクイズ(選択式)
Q. 認知症の薬について正しい説明はどれ?
A. ドネペジルは全ての認知症に効果がある
B. 薬は認知症を完治させることができる
C. 認知症の薬は症状の改善や進行抑制を目的とする
D. 薬は本人が嫌がっても必ず服用させるべきである
▶️ 正解はこちら(クリックで表示)
✅ C. 認知症の薬は症状の改善や進行抑制を目的とする
ドネペジルなどはアルツハイマー型認知症に使用され、進行を和らげるのが目的です。治す薬ではありません。