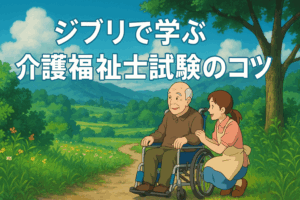🌱介護福祉士試験【生活支援技術⑮】
〜住環境の自立支援設計〜
🏠「家のつくり」を変えると、「できること」も変わる。
住み慣れた家でも、
年を重ねるとちょっとしたことが障害になる。
- ソファの高さが合わへん
- 廊下が狭くて通りにくい
- ベッドからトイレが遠い
そんな“生活のつまづき”を見つけて整えるのが、
「住環境の自立支援設計」やねん。
🛋住環境設計の目的は“自分でできる”を増やすこと
| 観点 | 具体内容 |
|---|---|
| 安全性 | 転倒・火傷・閉じ込めなどのリスク回避 |
| 利便性 | 動線・高さ・スペースの最適化 |
| 自立支援 | 「人の手を借りなくてもできる」環境づくり |
📐家具配置・動線の整え方
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ベッド・トイレ間の距離 | 夜間移動を短く/転倒リスク減らす動線に |
| 動線の広さ | **車椅子や歩行器も通れる幅(80cm以上)**を確保 |
| 家具の高さ | 椅子やテーブルは膝より高すぎず低すぎず(40〜45cm) |
| 不要物の除去 | 使っていない家具・コード・ラグの端などを片づけて転倒防止 |
🪜段差・手すりの工夫
| 対応 | 説明 |
|---|---|
| 段差解消 | スロープ/小さな段差なら段差解消材で対応 |
| 手すり設置位置 | 床から75〜85cmが基本。階段/トイレ/浴室などに重点配置 |
| 手すりの種類 | 横手すり→安定の保持、縦手すり→立ち座りに有効 |
🔧バリアフリー+ユニバーサルデザイン
- バリアフリー:困っている人の障壁を取り除く設計
- ユニバーサルデザイン:誰にでも使いやすく設計された環境(年齢や障害を問わず)
→ 例:自動ドア、センサー照明、段差レストイレ
🎞ジブリ風に言うなら?
🏡『借りぐらしのアリエッティ』の家を思い出して。
小さな体でも不自由なく暮らせるように、
全部が“自分のサイズ”に整えられてたやろ?
介護も同じや。
環境が人に合わせるだけで、「できること」はぐっと増えるんやで。
💡現場で活かせる小ワザ
- 🧼動線には物を置かない or カラーラインで進路を示す
- 🪑椅子やベッドはキャスター付きやと安定しにくい→ストッパー必須
- 📷家具配置のビフォーアフターを写真で記録して比較&共有
- 💡照明スイッチは手の届く位置+大きめボタンが安心
🧠試験で出るポイント!
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 自立支援設計 | 「できない」ではなく「できる環境をつくる」が目的 |
| 段差解消 | 転倒予防の基本。スロープ・手すり・色の変化で知らせるなど |
| ユニバーサルデザイン | 誰もが安全・快適に使えるよう設計された環境 |
🎯今日のキーワードは?
📌**「人が環境に合わせる」んやなくて、「環境が人に寄りそう」んやで。**
家そのものを“支援者”に変えていこう。
✏️おさらいクイズ(選択式)
Q. 住環境の自立支援設計として適切な対応はどれ?
A. 家具はなるべく多く配置し、掴まれる場所を増やす
B. 手すりの高さは膝の位置にすることで立ち上がりを助ける
C. 段差は気づかれにくいように同色で目立たせない
D. 動線を短くし、段差や手すりの設置で移動をサポートする