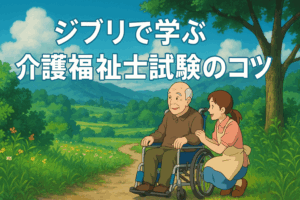🍀介護福祉士試験(障害の理解①)
🧠ここだけは抑えとけ|「障害」って何なん?定義と歴史的背景
〜時代とともに変わってきた“障害”の見方〜
✏️「障害」って、時代で見方がぜんぜん違った!
昔は「障害がある人=かわいそう」「社会とは別のところで生活する人」といったイメージが強かった時代がありました。
でも今は、「社会のあり方こそが障害を生んでるんちゃうか?」という考え方が主流です。
これを知るカギが、「医学モデル」→「社会モデル」への転換。
この違いがわかると、支援の考え方がグッと深まるで!
📘「医学モデル」と「社会モデル」って何やねん?
| モデル名 | 障害のとらえ方 | 支援の考え方 |
|---|---|---|
| 医学モデル | 本人の心身の“欠損”が原因 | 治療・訓練・できる限り健常に近づける |
| 社会モデル | 社会の側に“壁”がある | バリアフリー・合理的配慮・社会の変革 |
たとえば、段差があるから車いすの人が困る → それは社会の責任。
これが「社会モデル」の考えやねん。
👉 “ICF”っていう国際的な考え方も大事やで
ICF=国際生活機能分類(WHO)
これは「障害=できること/できないこと」だけやなくて、「環境・活動・参加」も含めて考えようっていう枠組みや。
🔑ポイントはこの3つ:
- 機能・構造(体や心の状態)
- 活動(できること)
- 参加(社会との関わり)
さらに「個人因子」や「環境因子」も評価対象になるねん。
🎞ジブリ風に言うなら?
『トトロ』で言うと、さつきが「お母さん、病院から帰ってくるかな…」と泣くシーン。
病気や障害そのものより、“どう寄り添い、待つか”が描かれてるやろ?
社会のまなざしこそが支えになる。それが今の障害理解や。
💡現場で活かせる小ワザ
- 「あれができない」じゃなく、「どうすればできるか?」で考える
- 環境を変えるだけで“障害じゃなくなる”こともある
- 本人の意欲や強みを引き出す声かけが大事やで
🧠試験で出るポイント!
- 医学モデルと社会モデルの違いは毎年問われるで!
- ICFの3構成要素(機能・活動・参加)はキーワード暗記や!
🎯今日のキーワードは?
✅ 医学モデル|✅ 社会モデル|✅ ICF(国際生活機能分類)
✏️おさらいクイズ(選択式)
Q. 「社会モデル」に基づいた支援として最も適切なのはどれ?
A. 障害を治療してできるだけ健常に近づける
B. 社会の側がバリアを取り除くよう工夫する
C. 本人の努力で社会に適応させる
D. 医学的診断に従って指導する