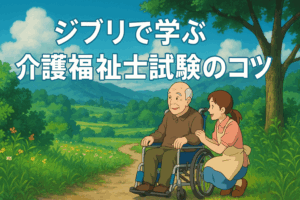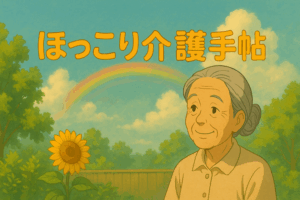🧠【本試験直前対策|介護過程 編】
✍️“考えて、振り返って、また考える”のが介護過程や
✏️試験でよく問われるのは、「どの段階で何をするか?」
介護過程は「アセスメント → 計画 → 実施 → 評価 → 再アセスメント」のループ。
どのタイミングでどんな視点が必要なのか、ズバリ問われるで!
📘頻出テーマ一覧(このへん重点)
| 項目 | 押さえるポイント |
|---|---|
| アセスメント | 多面的な情報収集と整理(生活歴・本人の思い) |
| 介護計画 | 個別性ある目標設定と支援内容の明確化 |
| 評価・再アセスメント | 変化の見極めとプラン修正 |
| チーム連携 | 多職種協働・情報共有・役割分担 |
| 倫理的配慮 | 人権尊重・プライバシー保護 |
✏️おさらいクイズ(全10問+解説)
Q1. アセスメントの主な目的はどれ?
A. 本人の希望のみを把握するため
B. 計画内容を家族に説明するため
C. 利用者の生活課題やニーズを多面的に把握するため
D. 支援者同士の意見をそろえるため
▶️ 正解はこちら
✅ **正解:C** → 生活歴・健康状態・本人の希望や困りごとを「多面的」に集めて整理することがアセスメントの基本。Q2. 支援計画において、個別性があると言えるのは?
A. 「毎日排泄介助を行う」とだけ記す
B. 「1日3回、Aさんの排泄リズムに合わせて誘導」
C. 「必要に応じて排泄介助」
D. 「他利用者と同様に支援する」
▶️ 正解はこちら
✅ **正解:B** → 利用者の「生活リズム」や状況に合わせた支援内容が“個別性”のある計画やで。Q3. 評価の段階で行うべきことは?
A. 支援が成功したかどうかだけを見る
B. 支援者の満足度を確認する
C. 支援内容と結果を照らし合わせて振り返る
D. 次の利用者への対応を検討する
▶️ 正解はこちら
✅ **正解:C** → 支援の結果がどうやったかを見て、「計画通りにいったか」「変更が必要か」を判断する段階や。Q4. アセスメントで収集すべき情報に当てはまるのは?
A. 支援者の予想
B. 他利用者の状況
C. 本人の生活歴や習慣
D. 介護保険の限度額
▶️ 正解はこちら
✅ **正解:C** → 本人の背景を知ることで、“その人らしさ”を支える支援ができるようになる。Q5. チーム支援の中で大切なことは?
A. 職種ごとの判断を分けて共有しない
B. 看護師が主導で全体を決定する
C. 介護福祉士・看護師・ケアマネが連携して情報共有する
D. なるべく各自の判断で進める
▶️ 正解はこちら
✅ **正解:C** → 介護は「チーム戦」。多職種連携・情報共有は欠かせへん。Q6. 再アセスメントを行うタイミングとして適切なのは?
A. 支援者の交代時
B. 利用者の状態が変化したとき
C. 曜日が変わったとき
D. 一定期間が経ったときのみ
▶️ 正解はこちら
✅ **正解:B** → 状況が変われば、「見直し」が必要。それが再アセスメント。Q7. 利用者中心の視点で計画を立てるとは?
A. 支援者が主体となって目標を決める
B. 本人の希望だけをすべて取り入れる
C. 本人の“生活課題”を基に支援内容を構成する
D. 家族の要望を最優先にする
▶️ 正解はこちら
✅ **正解:C** → 「課題」と「望む暮らし方」を土台にするのが、利用者中心の支援や。Q8. 倫理的配慮として正しいのは?
A. 情報はできるだけ広く共有する
B. 本人の同意なく支援方針を決定する
C. プライバシーを尊重しつつ情報を共有する
D. 家族がいれば本人の意思は不要
▶️ 正解はこちら
✅ **正解:C** → 情報共有も大事。でも“人権尊重”が前提や。Q9. 記録のポイントとして不適切なのは?
A. 客観的な観察内容を記載する
B. 利用者の言動を事実として記録する
C. 支援者の主観的な感想中心に記録する
D. 気づきや変化も記録する
▶️ 正解はこちら
✅ **正解:C** → 主観ではなく「事実+気づき」が基本やで。Q10. 介護過程において最も重視されるのは?
A. 支援者の効率
B. 支援の速さ
C. 本人のQOL向上と自立支援
D. 記録の量
▶️ 正解はこちら
✅ **正解:C** → “考えて、試して、振り返ってまた考える” → その繰り返しが「自立支援」と「QOL」を高めるんや。🎯今日のまとめ
📌 介護過程は「考え方の地図」や。
地図を持って動けば、迷いにくい。
→ 試験でも、現場でも、「どの場面で何を意識すべきか」を見極めるんやで。
🧭 その一歩が、“その人らしい暮らし”を支える道になる。