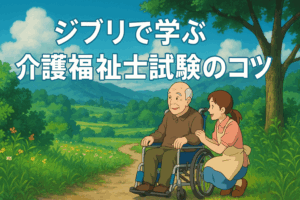🧑⚖️介護福祉士試験(認知症の理解⑬)
🧠ここだけは抑えとけ|“その人の人生を、ちゃんと支える”ってどういうことなんやろ?
〜 成年後見制度/虐待防止/意思決定支援 編 〜
✏️「支える」って、ただ代わりにやることやない
認知症の人をサポートする中で、
「全部こちらが判断して動けばええやん」って思ってまう場面もあるかもしれへん。
でもな、ほんまに大事なんは、
“その人自身の意思”を、どこまで尊重できるかなんよ。
もしも「黙って勝手に決められる」ようになってしもたら、
その人の人生、だれのもんかわからんようになるやろ?
だからこそ、認知症ケアでは「権利擁護」って視点がめっちゃ大切なんや。
📘本人の権利ってどんなもん?
認知症になっても、
「自分のことを自分で決める権利」は、当然ながら消えへん。
せやけど、判断が難しくなってきたときに、
誰かが勝手に決めたり、無理に従わせたりしたら、それは人権侵害になってまう。
だからこそ、介護や支援の現場では
🟡 意思決定を支える
🟡 弱い立場にある人を守る
この2つが大きな柱になるんや。
👉 成年後見制度って何のため?
本人の判断力が低下して、
契約や金銭管理が難しくなったとき――
そんなときに活用されるのが成年後見制度や。
「後見人」が代わりに契約したり、財産を守ったりしてくれる制度で、
🟡 正式な法律手続き(家庭裁判所)を経て
🟡 本人の利益になるような支援を行う
…って仕組みになってる。
ただし、本人の意思を無視して勝手に何でもやってしまうのはNG!
後見人であっても、常に「その人の想い」に寄り添うことが大前提やで。
🧠虐待防止も大事な支援のひとつ
認知症の人は、どうしても支援者との力関係が偏りやすい。
そのせいで、意図せんままに虐待が起こることもある。
虐待には、こんなんがある👇
- 身体的虐待(たたく・しばるなど)
- 心理的虐待(暴言・無視など)
- 経済的虐待(お金を勝手に使う)
- 介護放棄(ネグレクト)
- 性的虐待(不適切な接触)
「気づいたらやってもうてた」じゃ済まへんし、
利用者の小さなサインも見逃さんようにしたいな。
🎞ジブリ風に言うなら?
映画『ハウルの動く城』で、
ソフィーが「自分の意思」で歩き、自分の人生を取り戻していく姿…
あれってまさに、「意思決定支援」やねん。
たとえ魔法で姿が変わってしまっても、
“自分はこうしたい”という気持ちを支える存在がそばにいれば、
人はちゃんと前に進めるんやなって感じさせられるわ。
💡現場で活かせる小ワザ
- 利用者が「自分で選ぶ機会」をちゃんとつくる(メニュー・服・活動など)
- 判断が難しいときは「選びやすくする工夫」(例:2択で提示)
- 暴言や拒否の裏にある“気持ち”を汲み取る(無理やり従わせない)
- 「何か変やな?」と思ったら虐待の可能性も疑う(早めの連携・相談)
🧠試験で出るポイント!
| 用語 | 内容・補足 |
|---|---|
| 成年後見制度 | 判断能力が不十分な人を法的に支援。家庭裁判所が関与。 |
| 意思決定支援 | 本人の気持ちを尊重し、選びやすくする手助け。 |
| 権利擁護 | 本人の人権を守る考え方。虐待防止や制度利用も含む。 |
| 虐待の種類 | 身体的・心理的・経済的・性的・介護放棄などがある。 |
🎯今日のキーワードは?
📌**「その人の人生は、その人のもんやで」**
介護する側が勝手に奪わんように、
支えるんやなくて、“寄り添う”っていうスタンスが大切なんやで。
📚おさらいクイズ(選択式)
Q. 成年後見制度について正しいのはどれ?
A. 市役所が自動的に後見人をつける制度である
B. 判断力が低下しても、本人の意思は尊重されるべき
C. 後見人は本人の財産を自由に使ってよい
D. 後見人は虐待を見ても通報義務はない